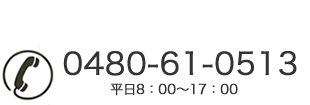会社概要
Company
ご挨拶
創業者(祖父)は夜間大学で土木を学びながら、戦前より東京都下水道局の技術者として建設業に携わり、戦後起業します。二代目(父)は大学で農業土木を学んだ埼玉県の技術者でした。先代たちは戦後から高度成長期にかけて道路や下水道、ほ場整備などの社会インフラを手掛けるとともに、まさに弊社のインフラストラクチャー(下部構造)を築き上げてくれました。
さて、時代はバブル崩壊までの安定成長期を経て、現在の低成長期へと移り変わりました。日本の社会インフラはその多くが高度成長期につくられ、今、更新時期を迎えています。人口減少、予算縮小などにより整備が困難とされるこの大量更新時代。これから私たちの世代が取り組まねばならない重要な仕事です。
工事の機械化が進み、新しい工法が次々と生み出された高度成長期にも困難な問題点はあったでしょう。しかし先人たちの知恵と努力が豊かな国を私たちに提供してくれました。
私たちもこの仕事を成し遂げ、その成果を実証し、さらにその先へ引き継ぐという使命のもと、日々努力を重ねる所存でございます。
代表取締役 小暮 一男
概 要
| 商 号 | こぐれ建設株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 埼玉県加須市土手2丁目5番41号 |
| 資本金 | 2,700万円 |
| 役 員 | 代表取締役社長 小暮一男 取締役 小暮年子 取締役 小野亜古 |
| 事業内容 | 土木一式工事、とび・土工、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事 |
| ISO9001 | 2001年3月 認証取得 |
| 主な取引先 | ・埼玉県県土整備部 行田県土整備事務所 ・埼玉県農林部 加須農林振興センター ・埼玉県企業局 地域整備事務所/水道整備事務所 ・水資源機構利根導水総合事業所 ・加須市役所 ・その他近隣市町村 土地改良区 |
沿 革
| 昭和24年10月 | 小暮與兵冶 小暮土建工業所を創業 |
|---|---|
| 昭和34年06月 | 有限会社小暮土建を設立 小暮芳男 代表取締役に就任 |
| 昭和47年10月 | 小暮年子 代表取締役に就任 |
| 昭和52年03月 | 株式会社小暮土建に組織変更 |
| 昭和53年11月 | 資本金の増資 (資本金1,350万円) |
| 平成02年10月 | 資本金の増資 (資本金2,700万円) |
| 平成09年04月 | こぐれ建設株式会社に商号変更 小暮一男 取締役に就任 |
| 平成13年08月 | 小暮一男 代表取締役に就任 |